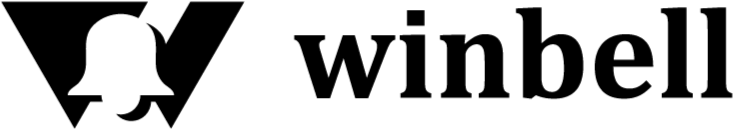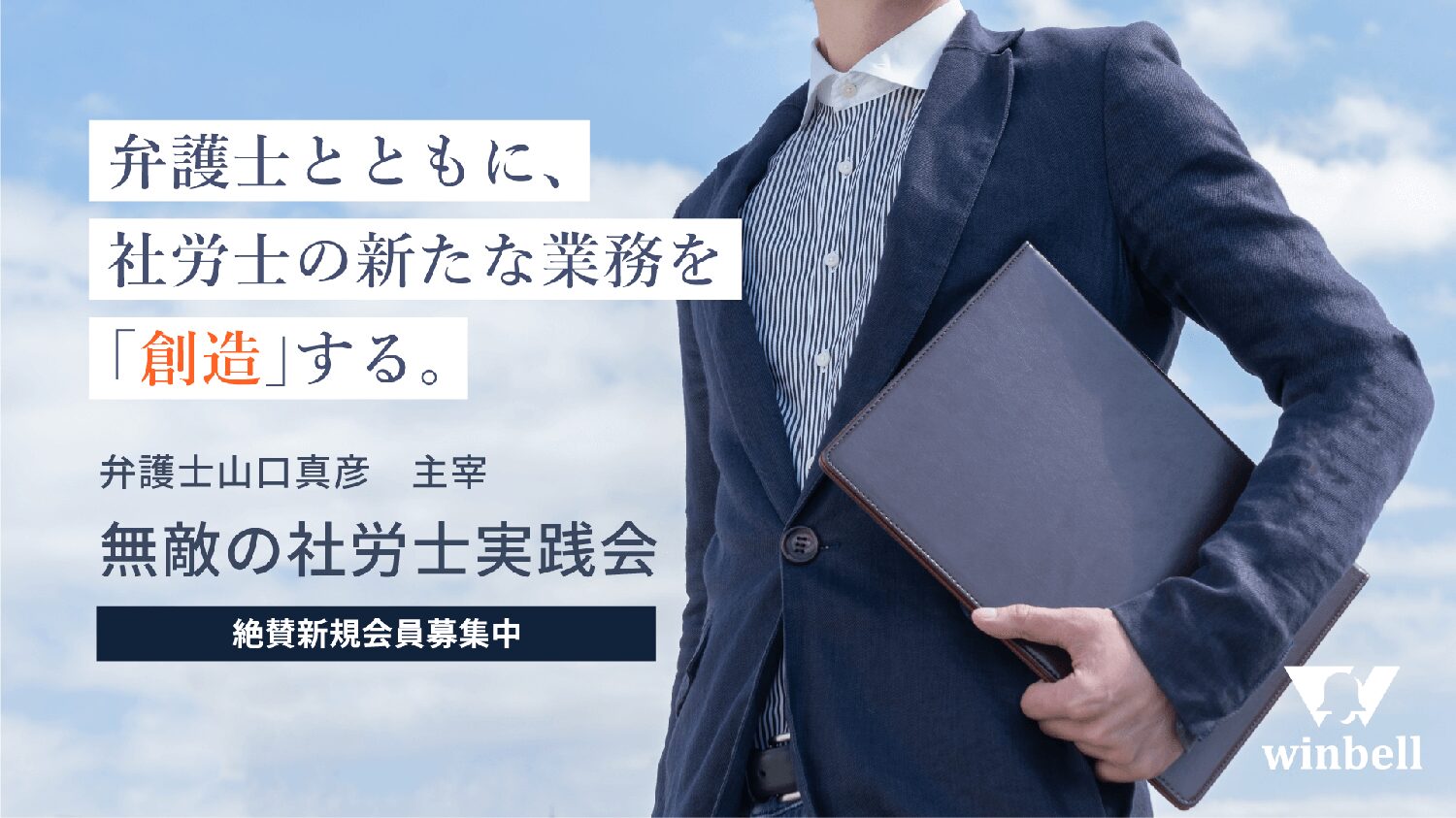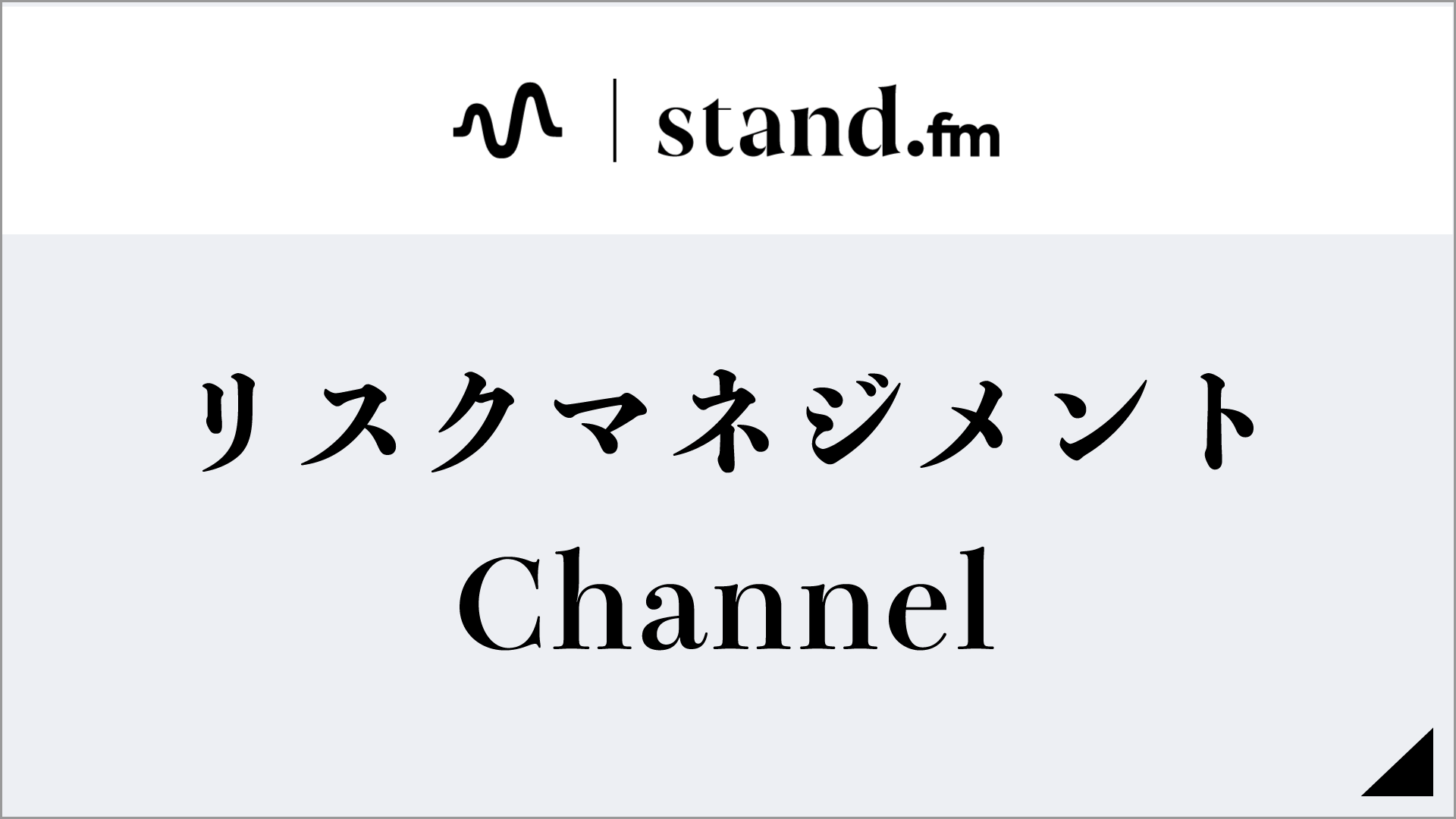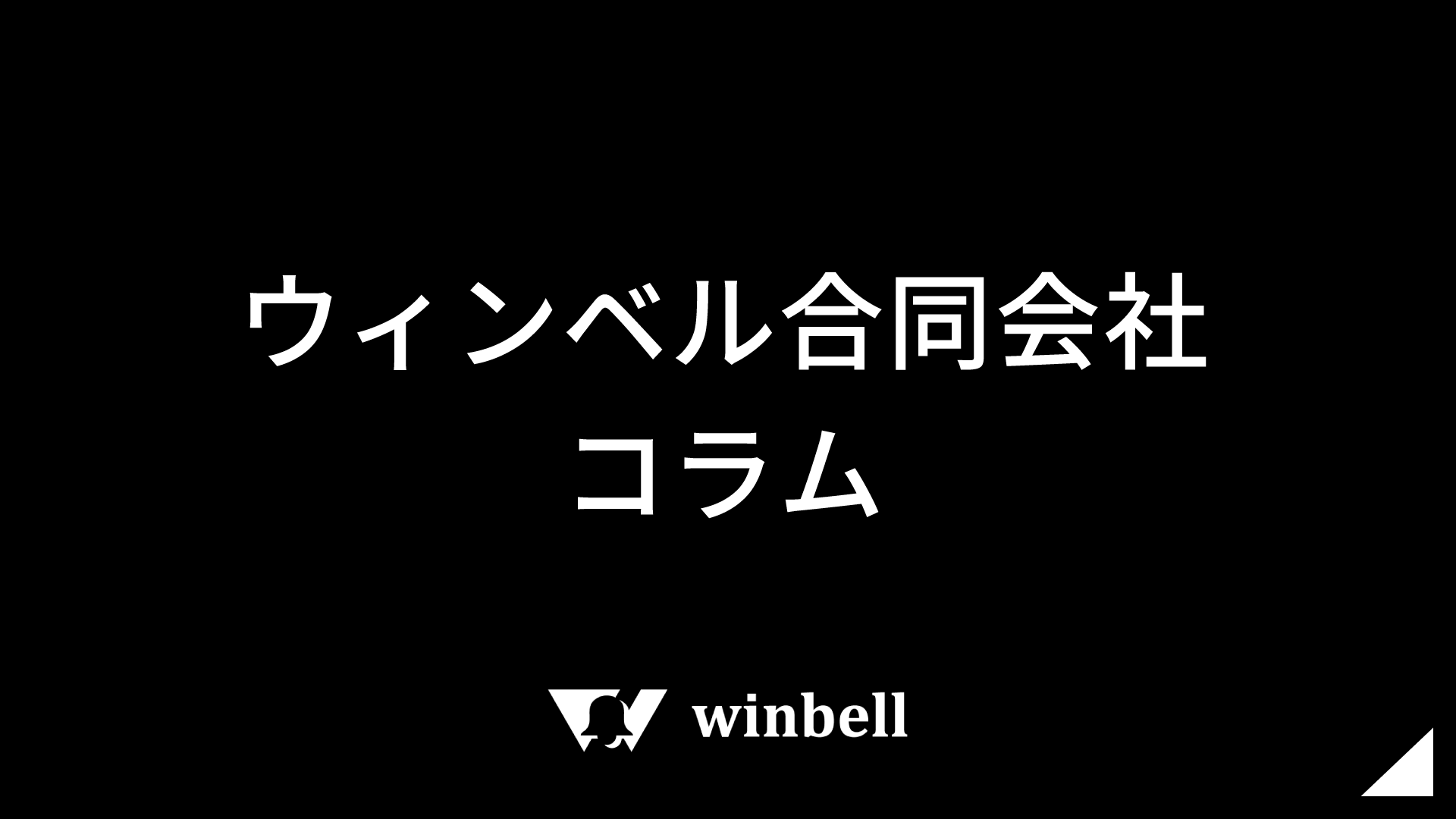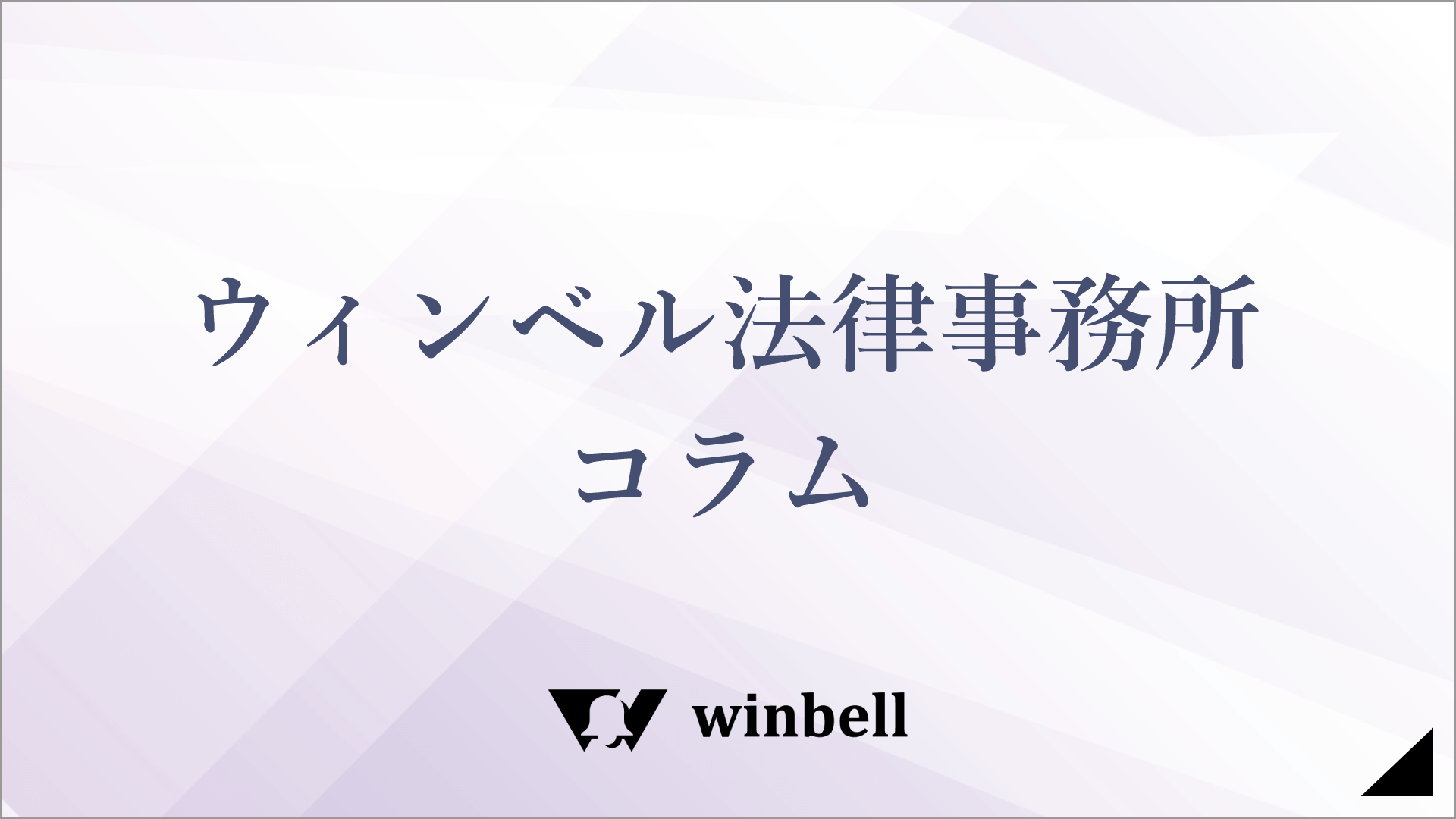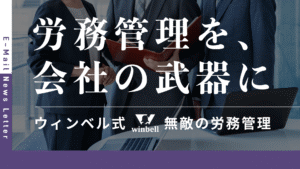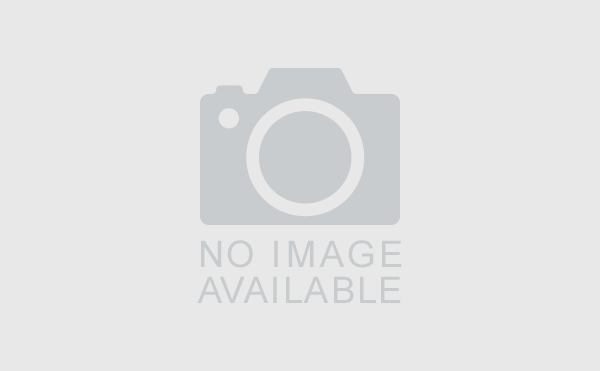【人材確保】入社祝い金の活用(その②)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.40

入社祝い金の活用
-その②-

ウィンベルの山口です。
このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、
- 私が目指す弁護士像
- 私をどのように活用してほしいか
- 皆さんにとって有益だと思う情報の共有
などを週3回、午前8時30分ころに配信します。
是非お知り合いにも紹介してください。
[登録用URL]https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm
金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
さて、本題です。
本日も入社祝い金についてお話したいと思います。
今回は、入社祝い金を導入する場合の注意点について解説したいと思います。
まず、入社祝い金が「賃金」に該当するかが問題となります。
労働基準法上の賃金に対する規制等を受けることになります。
そもそも、「賃金」とは労働の対価として支払われるものであり、福利厚生や恩恵的な給付は労働の対価ではないので「賃金」には該当しません。
入社祝い金の性質はどうでしょうか?
通常、入社祝い金は、労働契約の成立に基づいて支払われるもの(労働契約の成立と無関係に給付することは通常考えられない。)であることから、基本的には労働契約の合意内容に基づく給付になるかと思いますので、「賃金」に該当すると考えるべきです。
このように考えると、入社祝い金を支給する場合は、労働条件通知書や就業規則での明示が必要になります。
入社祝い金をどの人材にも同額を給付するのであれば就業規則に明示するのが便利でしょうし、人材に応じて入社祝い金の額を変える場合は、個別の労働条件通知書で明示する必要があります。
次に、入社祝い金に関するトラブルについて紹介します。
導入を検討される際は、この点も考慮いただければと思います。
最も多いトラブルは、やはり返還請求です。
入社祝い金を支払ったにもかかわらず、早期に退職した場合、やはり会社としては入社祝い金の返還を求めたいですよね。
では、会社は返還を求めることはできるのでしょうか。
この点に関して、裁判例がいくつかあります。
などです。
これらの裁判例を見ると皆さん同じ感想を持つと思います。
「高くね?」
そうですよね。
そもそも、裁判してでも回収したいぐらいの金額が基本となるので裁判例は高額になりがちになります。
ただ、裁判所の考え方は参考になりますので、簡単に説明すると、①②の裁判例はいずれも「一定期間内に中途退職した場合は、給付したお金を返還しなければならない」という合意をしていましたが、いずれも返還はしなくていいという判断でした。
このような裁判例を踏まえて対策を考えると、給付ではなく貸付にすることも考えられます。
貸付にして一定期間勤務したら、返還を免除するという方法です。
この方法は、確かに返還請求ができるという点では効果的ですが、そもそも、入社祝い金が貸付となると、従業員側からすると、あまりメリットがないようにも思います。
また、仮に貸付にしたとしても、その額や返還を免除するために必要な期間によっては無効になる可能性があります。
このように裁判例を読み解いていくと、やはり入社祝い金は、人材確保の必要性とのバランスを考慮しつつ、少額に留める(返ってこなくてもあきらめのつく金額)べきです。
具体的には、予定の月給の10%程度の給付がいいかと思います。
次回は、入社祝い金に関するその他の注意点について解説いたします。
その上で、実際に入社祝い金を給付する場合の合意書を紹介したいと思います。
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
バックナンバーはこちら 弁護士山口への質問箱