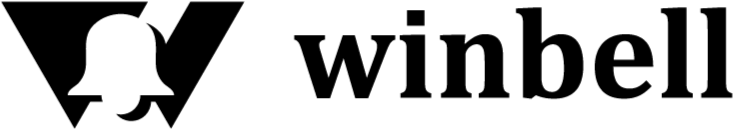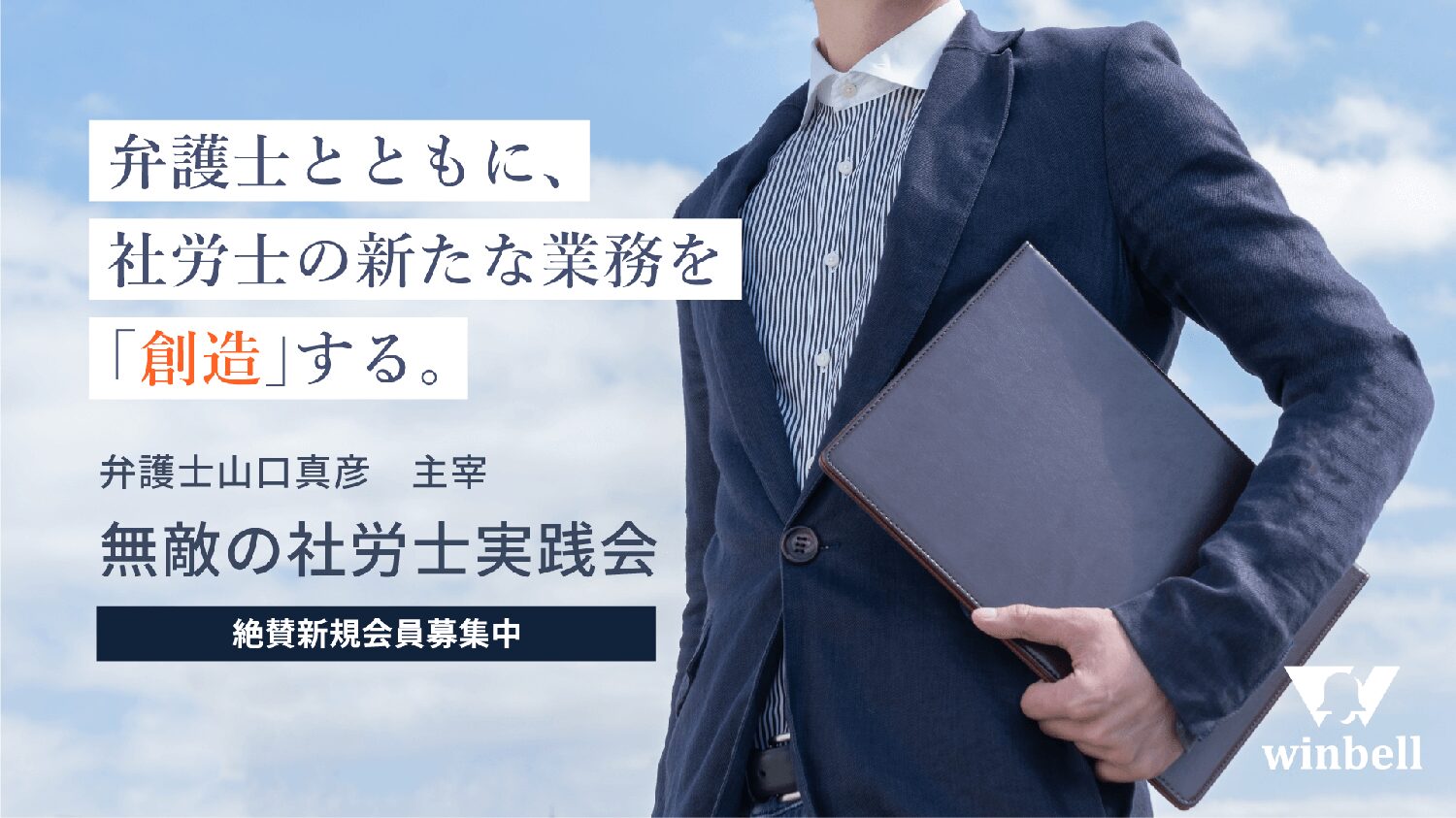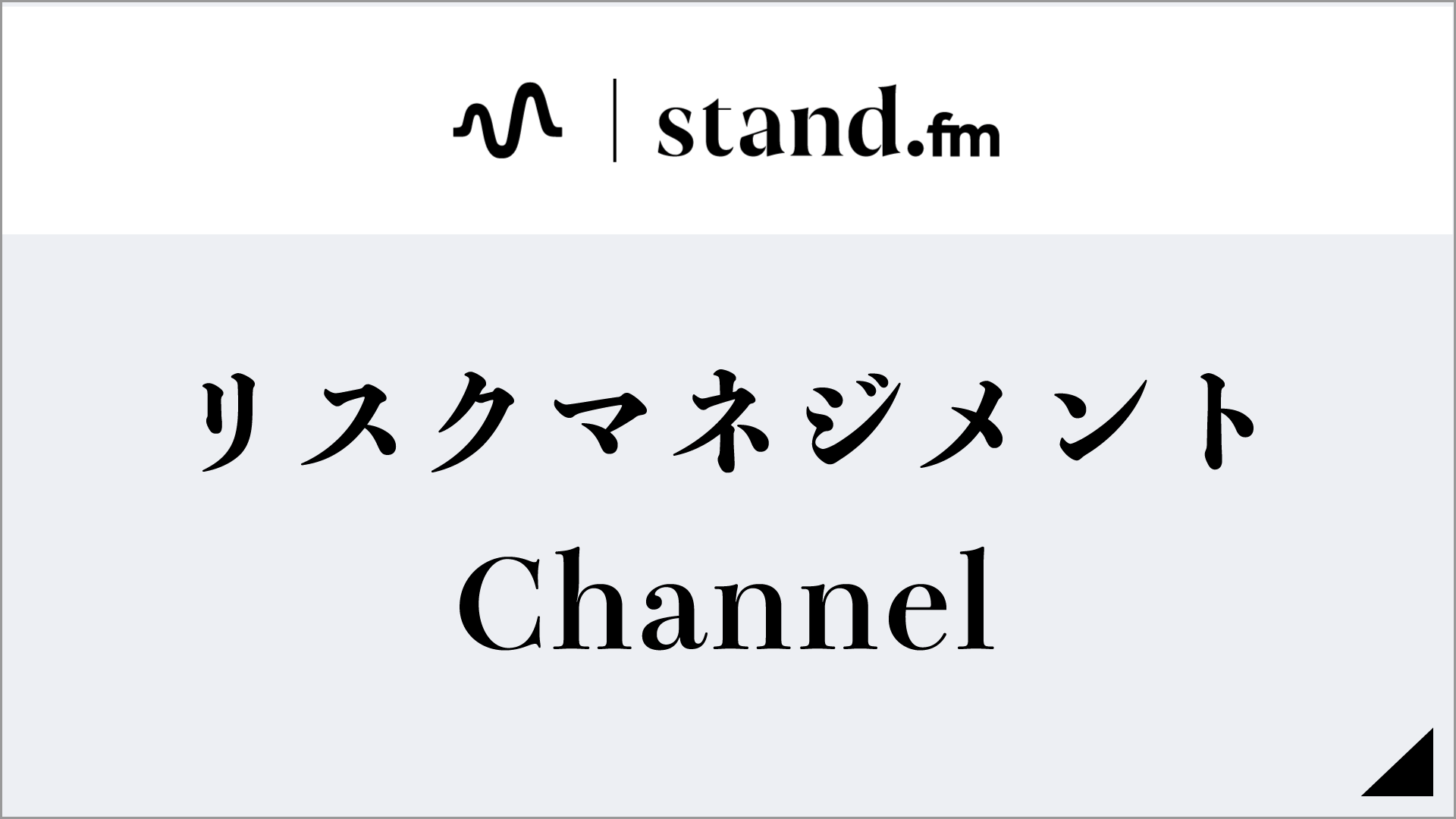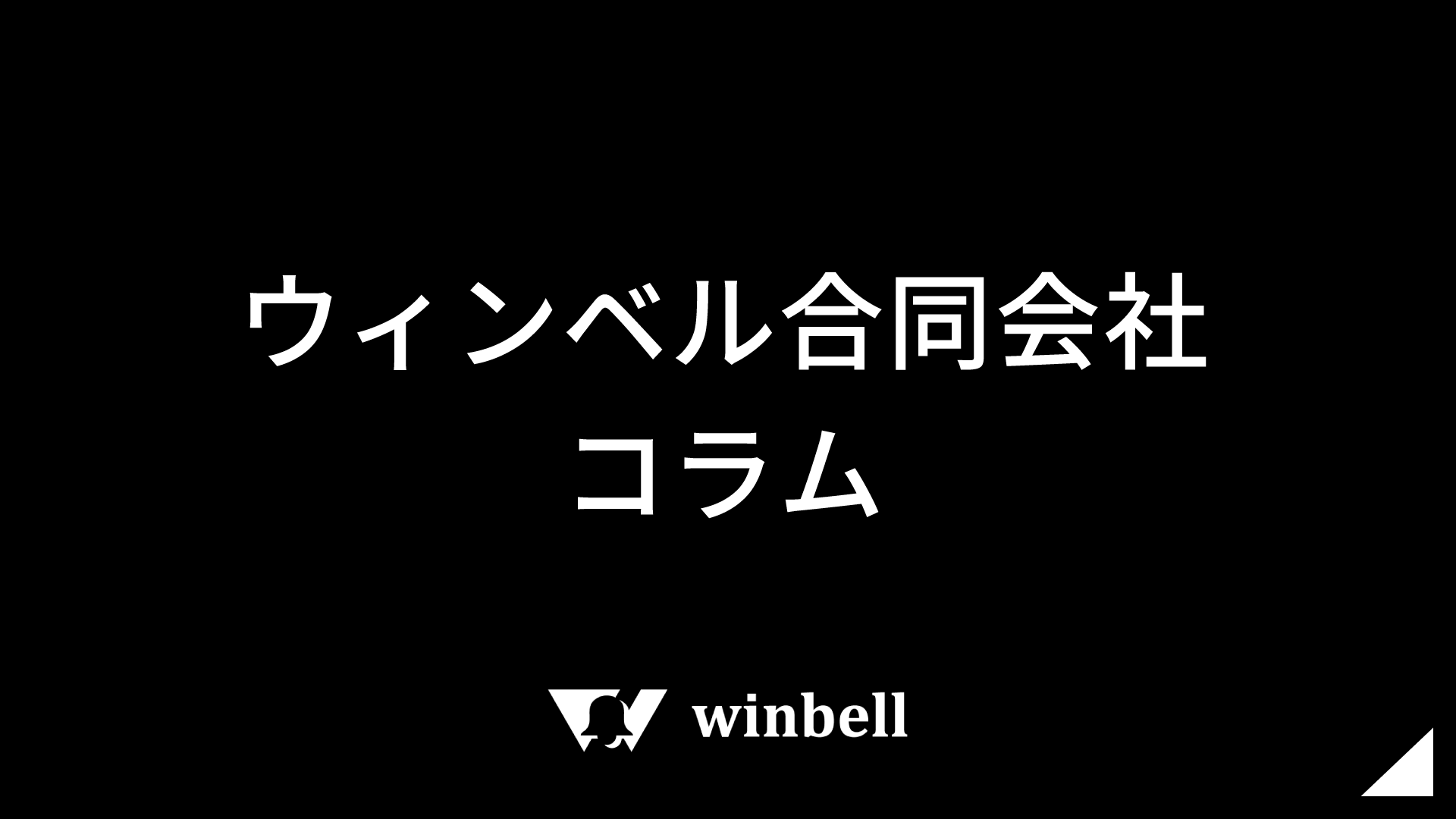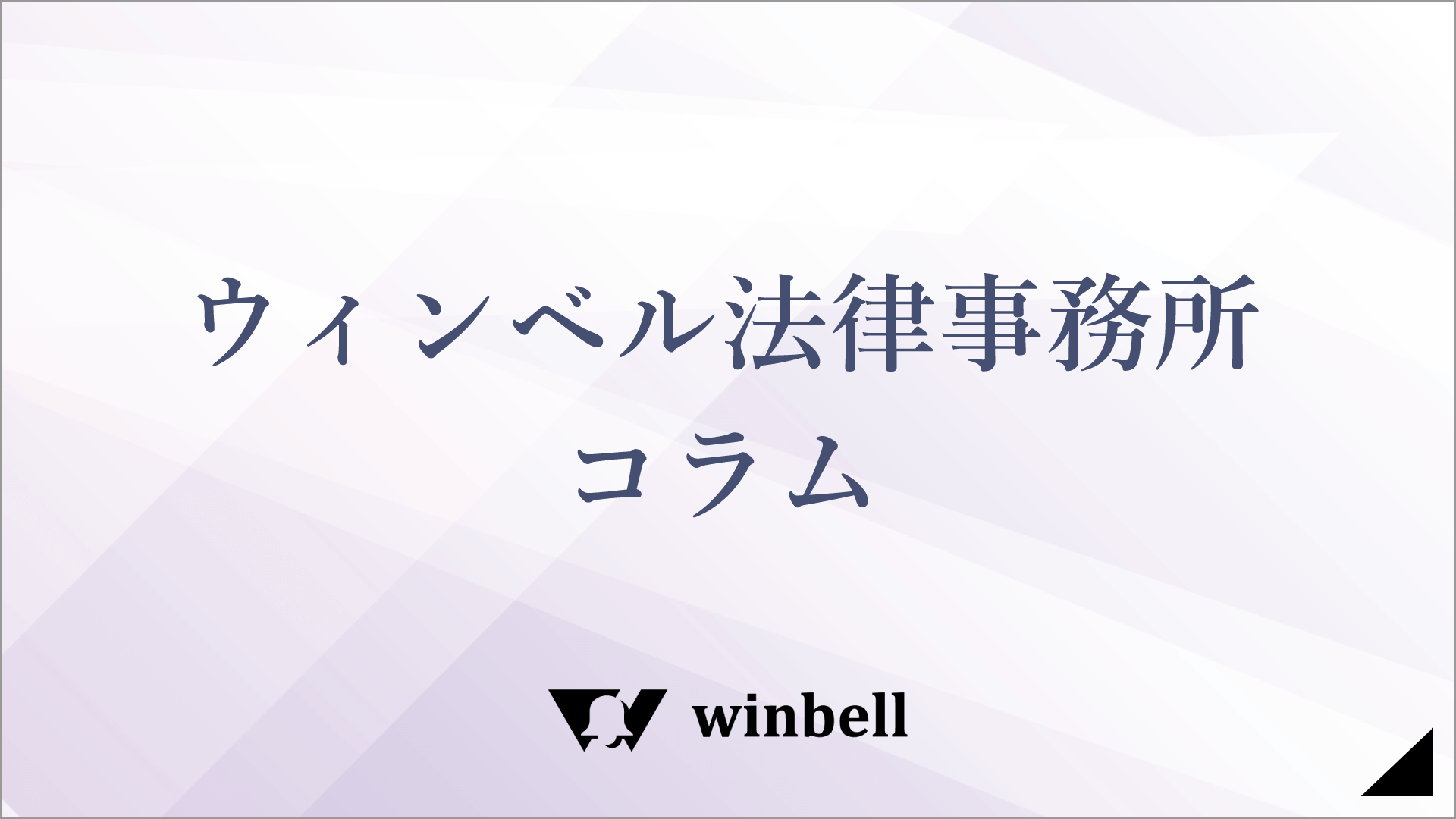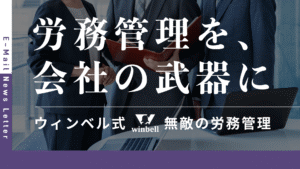就業規則の真の効果|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.38

就業規則の真の効果

ウィンベルの山口です。
このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、
- 私が目指す弁護士像
- 私をどのように活用してほしいか
- 皆さんにとって有益だと思う情報の共有
などを週3回、午前8時30分ころに配信します。
是非お知り合いにも紹介してください。
[登録用URL]https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm
金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
さて、本題です。
本日は、就業規則の真の効果というテーマでお話したいと思います。
先日、とあるクリニックから就業規則の相談を受け、就業規則の作成及びスタッフへの説明会を実施するという内容でご依頼をいただきました。
まずは、院長と打合せをして、どのような就業規則を希望するかのヒアリングを行いました。
院長は、
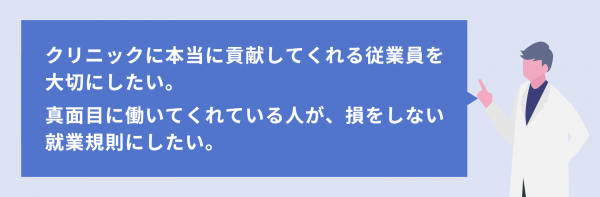
という希望でした。
この視点は、就業規則を作成する上で非常に重要な視点だと思います。
中小企業でのあるあるですが、
と言って、厚生労働省のホームページで公開されているモデル就業規則をちょっといじって、自社の就業規則とする。
もちろん、法律上就業規則の作成・届出義務があることは事実なので、間違っていないのですが、そもそも厚生労働省のモデル就業規則は何に基づいて作成されているでしょう?
当然ですが、「労働法」をベースとして作成されています。
では、「労働法」ってどんな法律でしょうか?
「労働法」は、労働者を守る法律です。
会社と一従業員を比較したときに、その資本力や交渉力において明らかに会社の方が強いので、労働者側に下駄を履かせて会社と対等に交渉ができるようにしているのが労働法です。
つまり、労働法には「会社を守る」という視点はないのです。
では、会社を守らなければならないような事態が生じるのはどのような場面でしょうか?
そうです。
問題のある従業員を雇ってしまった場合や既存従業員が問題社員化した場合です。
たとえば、業務命令に従わない、ハラスメントをする、遅刻が多い、報告書で嘘をつく、協調性がない・・・などです。
このような従業員に下駄を履かせていいでしょうか?
下駄を履かせて会社を守れるのでしょうか?
このような場面を考えてみてください。
協調性に欠ける従業員がいて、その対応に周囲の真面目な従業員が苦慮し、真面目な従業員が心が折れて退職してしまう・・・
経営者としてはこのような事態は絶対に避けるべきです。
まさに、先ほどの院長の「本当に貢献してくれる従業員を大切にしたい」「真面目に働いてくれている人が損をしないようにしたい」という視点です。
就業規則を労働法だけに基づいて作成してしまうと、問題のある従業員にまで下駄を履かせてしまい、本来社長が守らなければならない従業員を守れない(=会社を守れない)状況を作ってしまいます。
そこで、重要になる考えが、就業規則を労働法だけに基づいて作成しないという点です。
民法にも基づいて作成するということです。
この考えに基づいて作成された就業規則は、真の効果を発揮します。
今回依頼を受けたクリニックでは、私が従業員への新しい就業規則の説明会を行ってから1か月で、2名の従業員が退職を申し出たそうです。
院長は、この事実を喜んで私に報告してくれました。
実は、この2名の従業員は、以前から協調性に欠け、周りの従業員がその対応に苦慮していた従業員だったそうです。
院長からは
最初の打合せで伝えた『クリニックに本当に貢献してくれる従業員を大切にし、真面目に働いてくれている人が損をしない』という希望を具現化した就業規則を作成してくれてありがとう。
と感謝されました。
私は、これが就業規則の真の効果だと思っています。
ぜひ自社の就業規則がどのような視点で作成されているか、クライアントの就業規則がどのような視点で作成されているかを確認してみてください。
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
バックナンバーはこちら 弁護士山口への質問箱