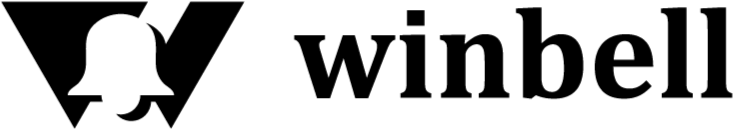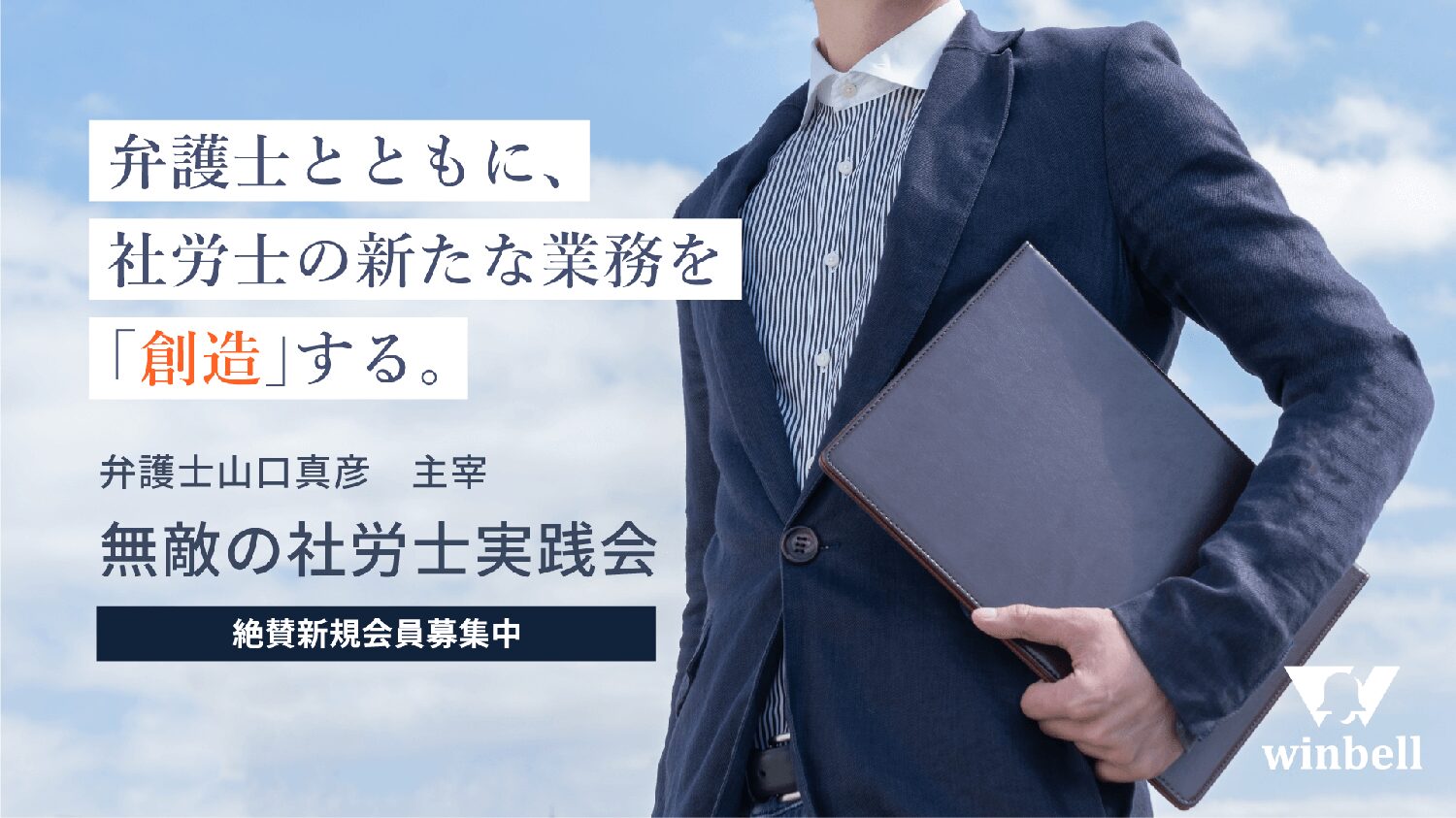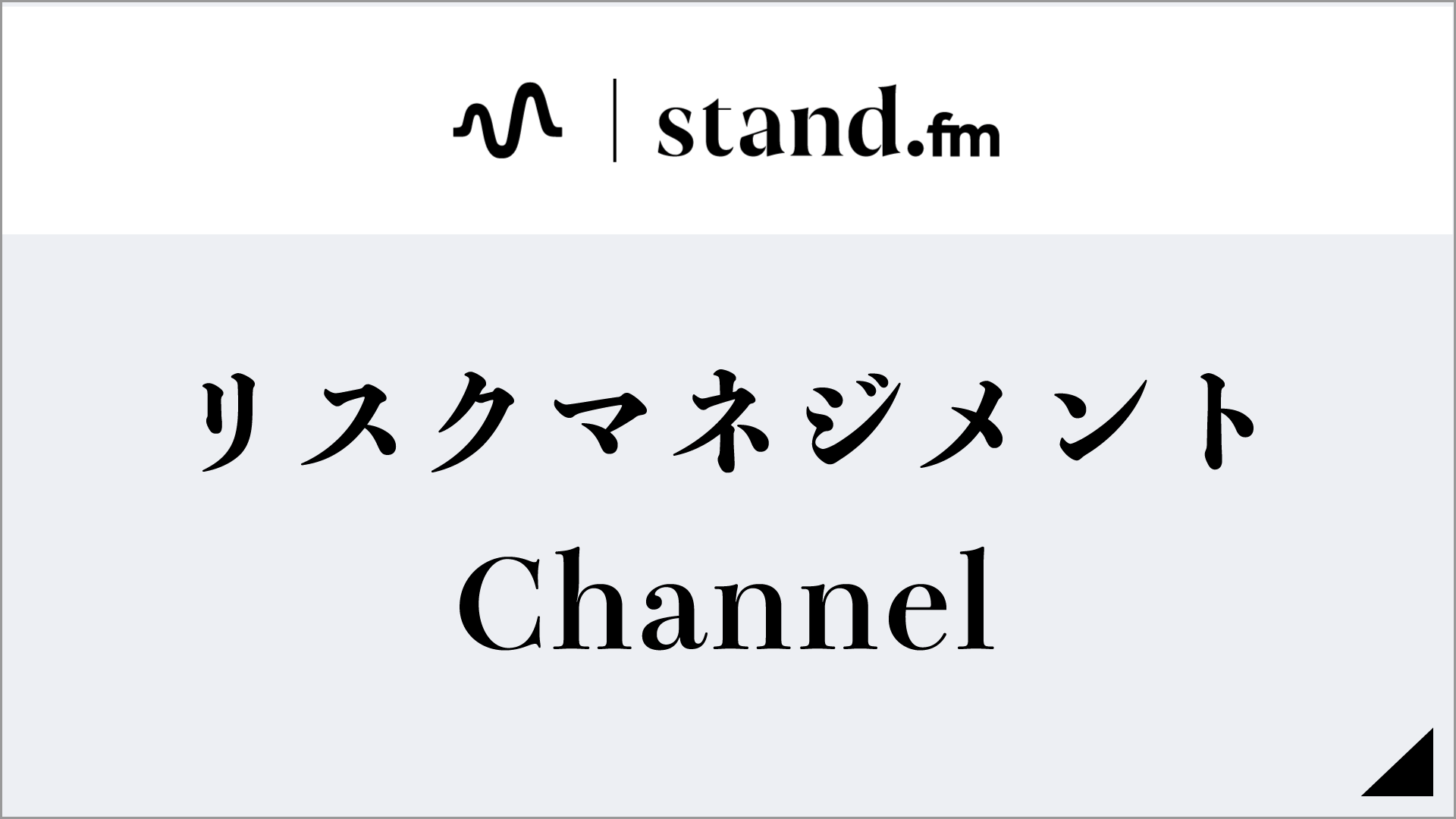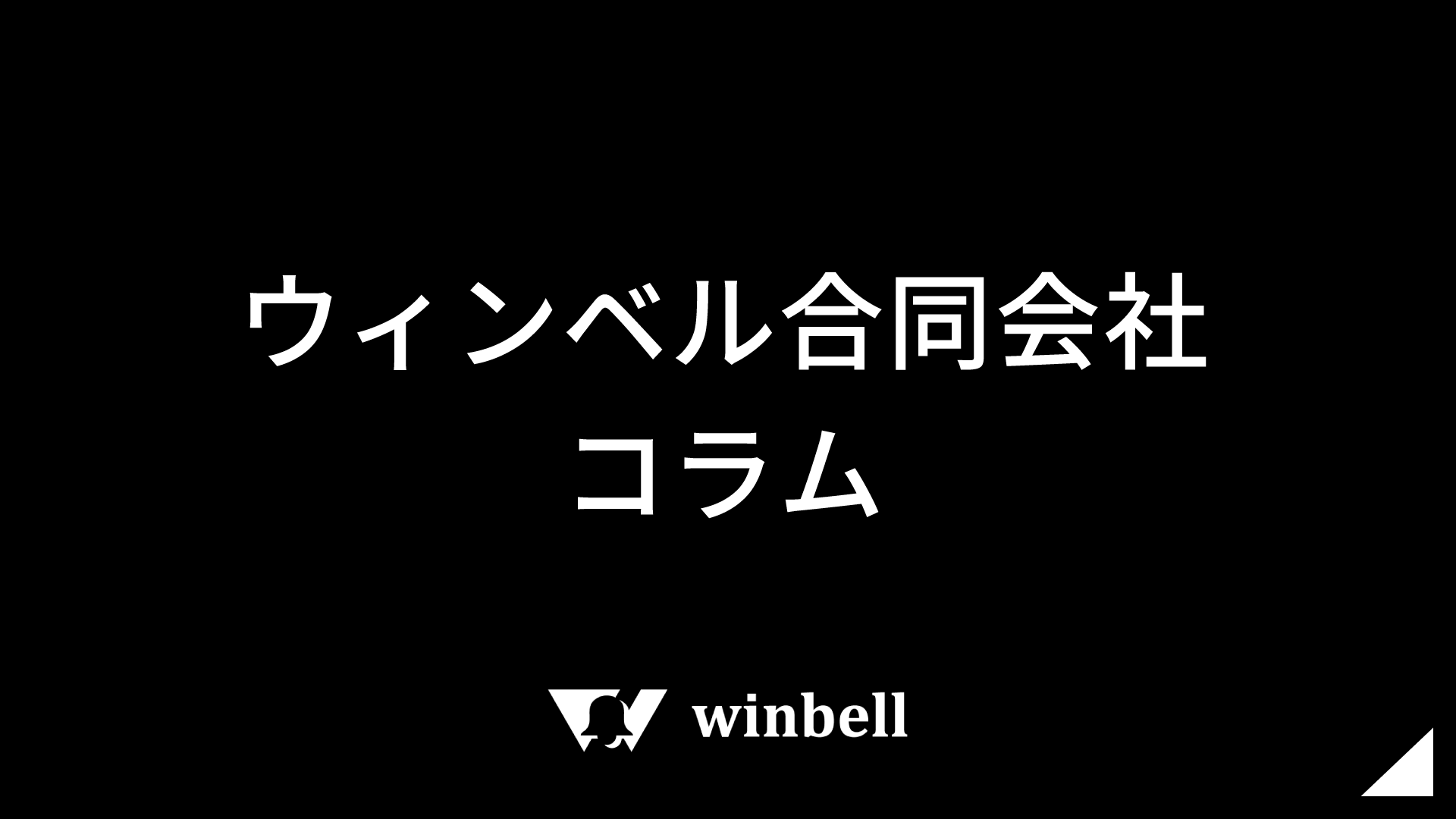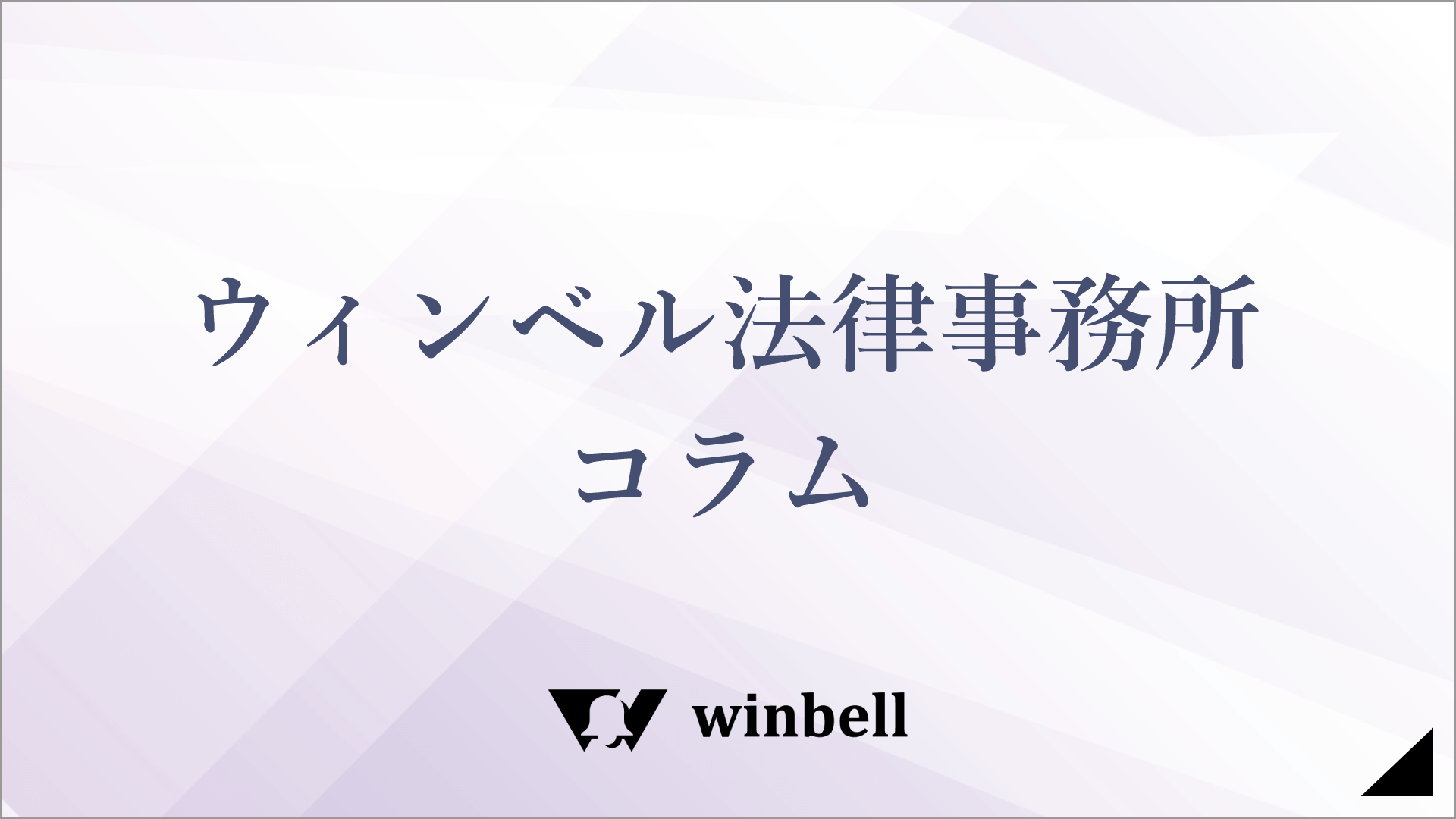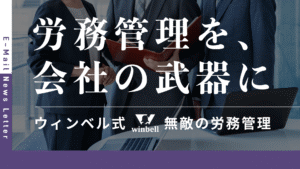質問をいただきました!-副業トラブル(その①)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.34

質問をいただきました!
-副業トラブル その①-

ウィンベルの山口です。
このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、
- 私が目指す弁護士像
- 私をどのように活用してほしいか
- 皆さんにとって有益だと思う情報の共有
などを週3回、午前8時30分ころに配信します。
是非お知り合いにも紹介してください。
[登録用URL]https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm
金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
さて、本題です。
今回は、前回までお伝えしてきました副業に関して、質問をいただきました。※ご質問については、メルマガの下部に山口への質問箱というのがいつの間にか設置されていますので、ご活用ください。
今回の質問はこちらです。
いつも有益な情報をありがとうございます。
先日の副業の記事で、副業を認めた場合、労務管理が複雑になることは理解しました。
一方で、今後は副業を認めざるを得ない状況になると思います。
そうした中で、副業が原因で過重労働等のトラブルになった場合、本業先と副業先との責任問題はどのような形になるのでしょうか?
クライアントが本業先になる場合も副業先になる場合もあると思うので、それぞれの立場で責任を回避(もしくは責任を軽減)するためにどのような対策が考えられますか?
いい質問ですね!(池上彰風)
この点については参考になる裁判例がありますので、その裁判例の解説をしつつ、ご質問に回答したいと思います。
まずは、裁判例を紹介します。
- 大器キャリアキャスティング事件(大阪高判令和4年10月14日)
-
事案の概要
Xは、Y社と雇用契約を締結し、ガソリンスタンドで深夜帯のシフト(主に、午後10時~翌午前2時まで)で勤務していた。
Xは、A社とも雇用契約を締結し、同じガソリンスタンドで午前7時から午後10時までの勤務をしていた。
なお、Xが勤務していたガソリンスタンドは、A社のガソリンスタンドであり、A社はY社に対してガソリンスタンドの運営を委託していた。
Xは、休みなく勤務していたため、体調を崩し、安全配慮義務違反等を理由にY社及びA社に対して、損害賠償請求をした。
Y社のマネージャーは、Xの体調を考慮して、事前にA社との雇用契約に基づく就労をやめるように求め、それに対してXは了承していた。
結論- 本業先(Y社)の責任:安全配慮義務違反あり
- 副業先(A社)の責任:安全配慮義務違反なし
このような裁判例です。
今回はまず本業先の責任について解説します。
いかがでしょうか?
Y社は、Xに対してA社での就労をやめるように求め、それに対してXも了承しているのに、それでも責任を負うの!?というのが素直な感想ではないでしょうか?
私もそう思います。
ちなみに、この裁判例の第1審は、Y社の責任を否定しています。
では、なぜ第2審では一転責任が認められたのか?
その理由は、この事例の特殊性にあります。
まず、Y社が負う安全配慮義務の内容は、
です。
そして、今回の事例では、Xの勤務先がY社の契約とA社の契約で同じガソリンスタンドであったことから、「Y社がA社に問い合わせるなどしてXの労働日数、労働時間について把握できる状況であったでしょ?だったら、それをすべきだったよね。」という論理でY社の責任を認めています。
これからわかることは、副業による長時間勤務がXが積極的に選択した結果であったとしても、本業先は可能な限り副業先の勤務状況を把握し、その状況に応じて労働者が求めるシフトを拒否するなどの措置をすべきということになります。
ただし、副業先の勤務状況を把握することは今回の事例のような例外的な場合でない限り困難です。
そこで、より一般化すると、
と思います。
一方、シフト制ではなく固定的な勤務時間の場合は、それまで短くする必要まではありません。
代わりに、副業を辞めさせるような働きかけを行い、その証拠を残しておくことが重要になると思います。
なお、今回のようにY社の責任が認められたとしても、Xの積極的な選択により過重労働が発生した場合については、Xのこの選択がXの過失として過失相殺がなされることになります。
ちょっと長くなりましたので、まとめると、本業先での対策としては、
- 労働者の自己申告により副業先の労働状況を定期的に把握する。
※今回の裁判例のような特殊なケースでは、自己申告ではなく本業先が積極的に把握する。 - 労働者の健康状態に異変がないかを定期的に確認する。
- 長時間労働や健康状態の悪化を認識した場合、本業のシフトを入れない、本業の時間外労働を抑制、副業をやめるように求める、副業の許可を取り消す可能性を予告するなどの措置を講じる。
これが本業先の対策になります。
本日は以上です。
次回は副業先の対策を見ていきたいと思います。
それでは、よい一日を。
バックナンバーはこちら 弁護士山口への質問箱