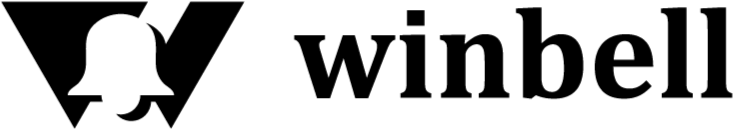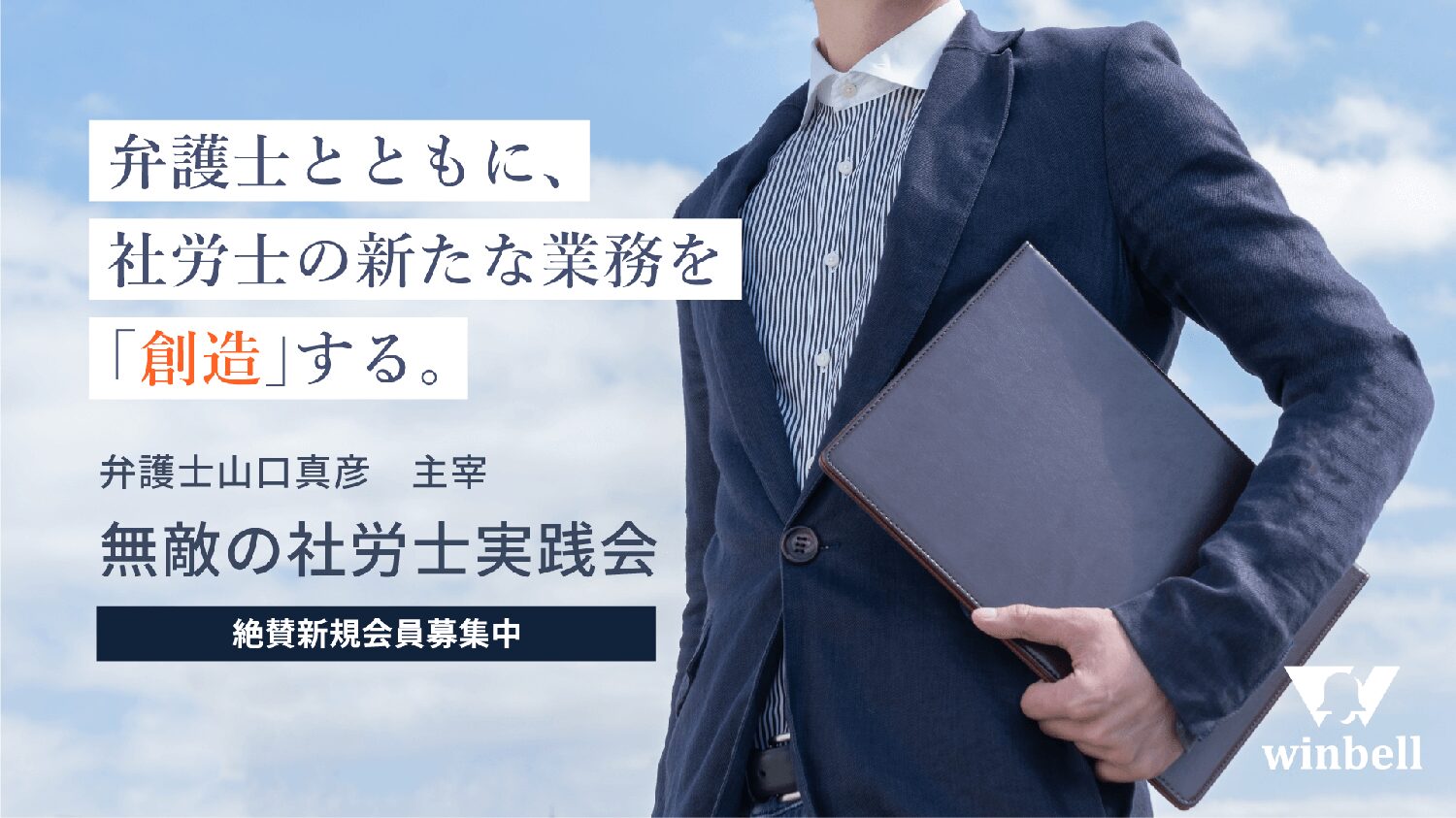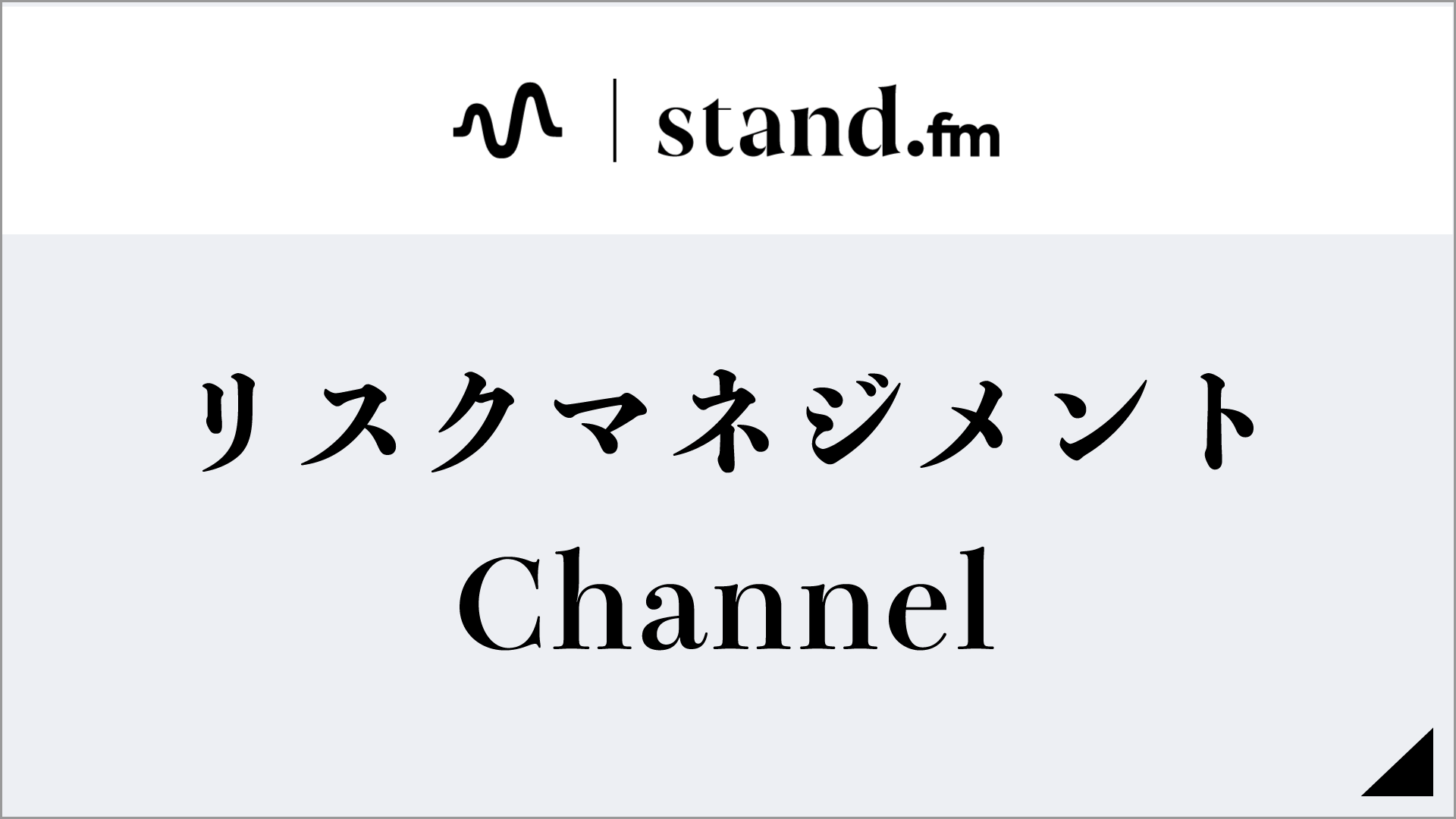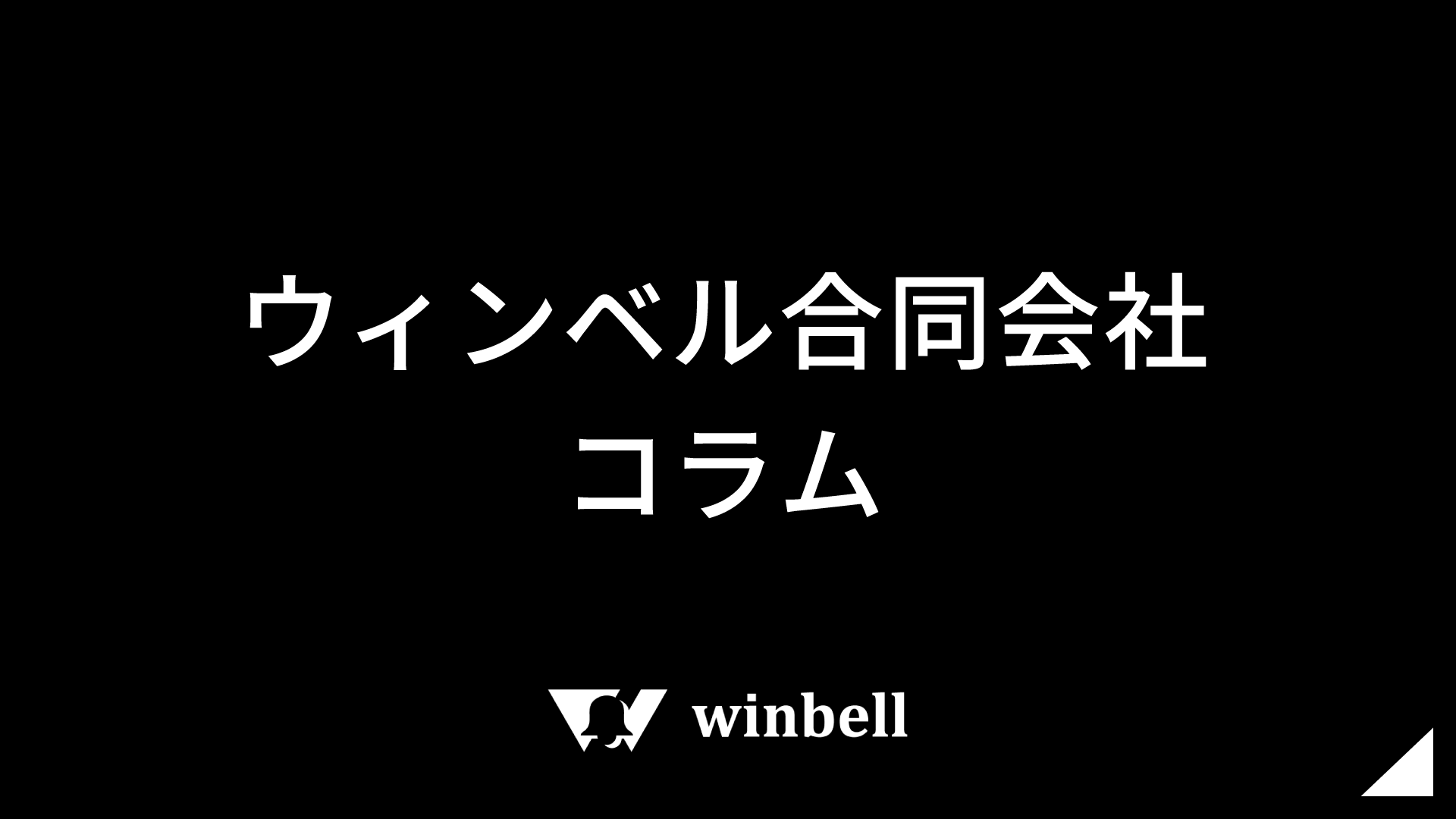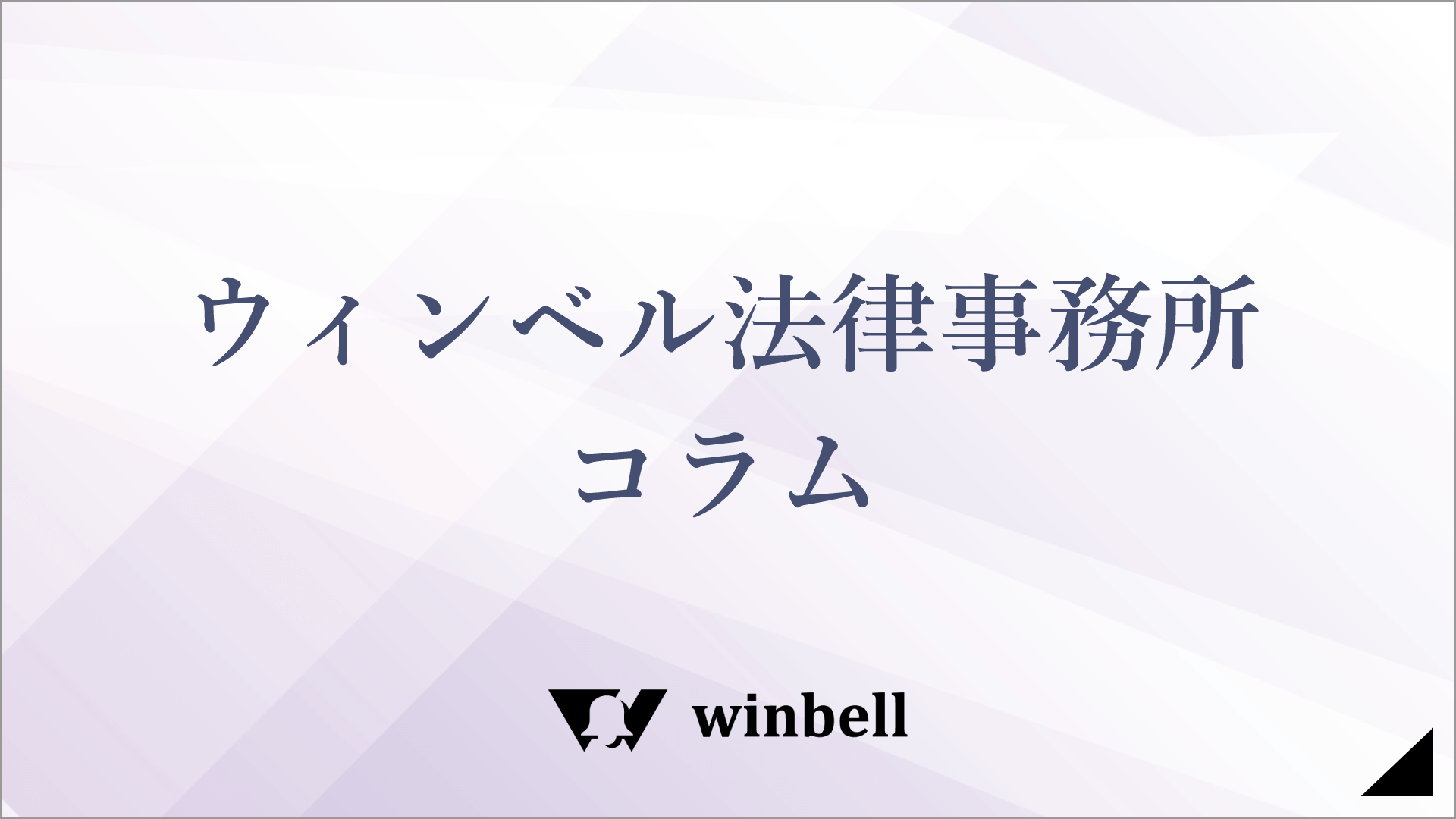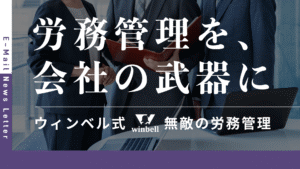兼業・副業認める?(その③)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.32

兼業・副業認める?
-その③-

ウィンベルの山口です。
このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、
- 私が目指す弁護士像
- 私をどのように活用してほしいか
- 皆さんにとって有益だと思う情報の共有
などを週3回、午前8時30分ころに配信します。
是非お知り合いにも紹介してください。
[登録用URL]https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm
金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
さて、本題です。
前回に引き続き、今回も副業・兼業についてお話したいと思います。
相談内容はこちらでしたね。
昨年内定を出した今年の4月から入社予定の内定者から次のようなメールが届きました。
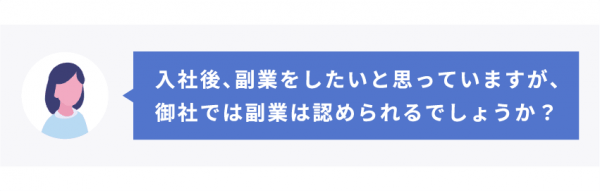
これに対し、弊社では、兼業・副業を認めていませんでしたので、
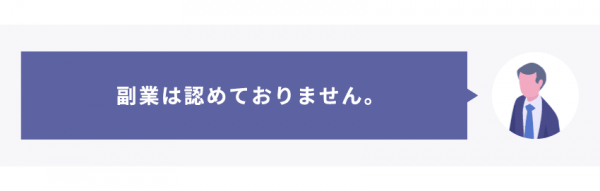
と回答したところ、内定を辞退されてしまいました。
今後、内定者からこのような問い合わせがあった場合、どう回答すべきか、また既存の従業員から副業のニーズが出てきた場合どう対応すべきでしょうか?
前回、許可制を採用した場合の就業規則案をお伝えしました。
その中で、「申請書には副業先の労働条件を詳しく書いてもらうべき」とお伝えしました。
それは、副業を認めた場合、労働時間は副業先の労働時間と通算することになるためです。
たとえば、山口が本業であるA社と先に雇用契約を締結し、A社入社後に許可を得て、副業先であるB社と雇用契約を締結したとします。
この場合、山口がA社で8時間勤務し、その後B社で2時間勤務すると、その日の山口の労働時間は10時間となります。
つまり、1日8時間という法定労働時間から2時間超過するため、2時間分の時間外割増賃金が発生します(割増賃金の支払い義務は、後から雇用契約を締結したB社にあります。)。
このように労働時間は通算されますし、時間外労働については、月100時間、複数月平均80時間という上限規制がありますので、副業先の労働条件もA社は把握しなければなりません。
把握の方法は基本的に本人からの申告しかありませんので、申請書で細かく記載してもらう必要があるわけです。
なお、労働時間の管理については、簡便な管理モデルもありますので、興味のある方はご覧ください。
本日は以上です。
次回は、これまでの話を踏まえて、冒頭の相談内容について私なりの回答をお伝えしたいと思います。
それでは、よい一日を。
バックナンバーはこちら