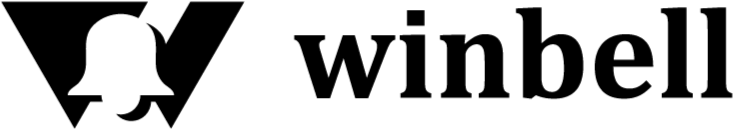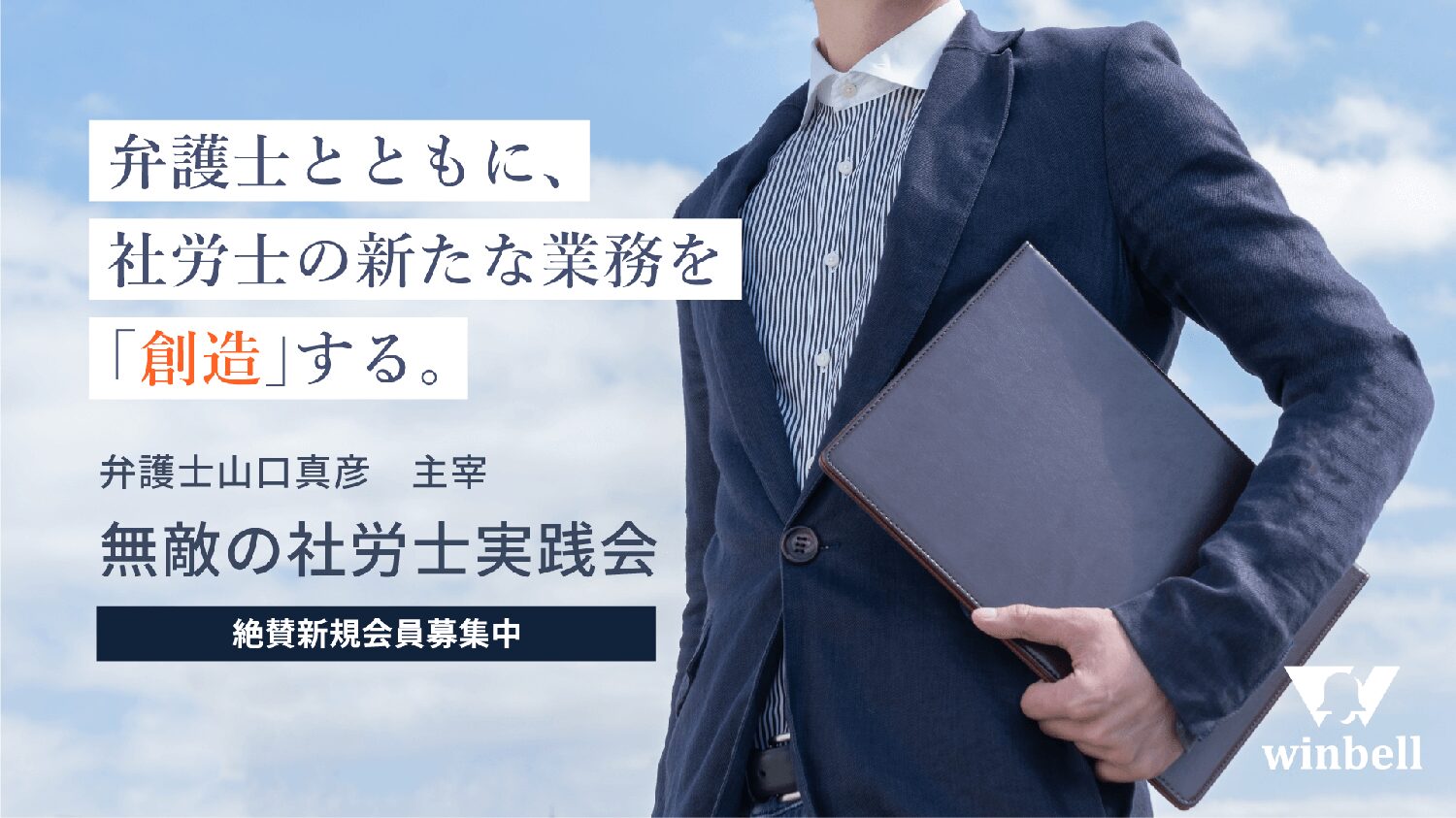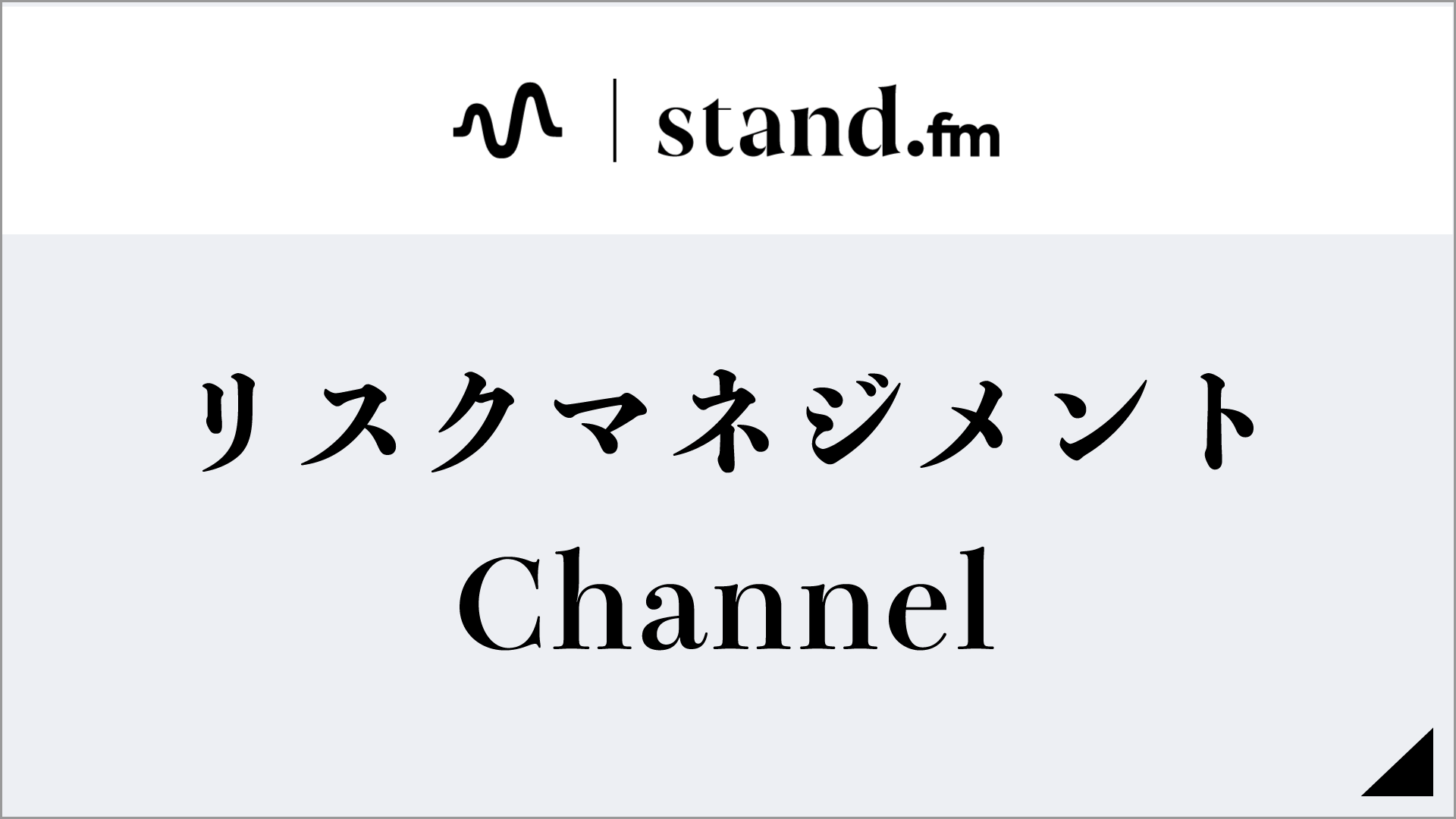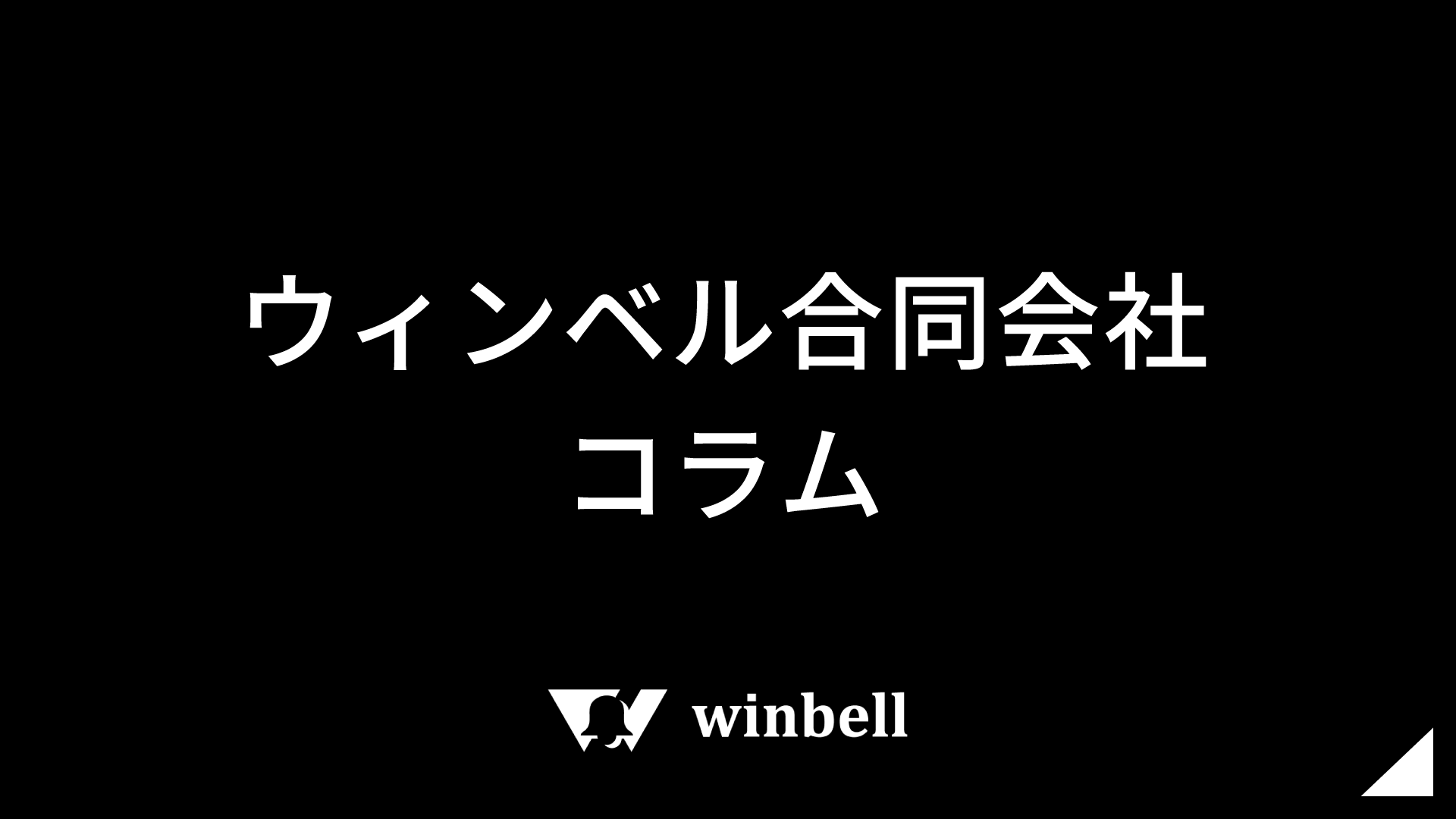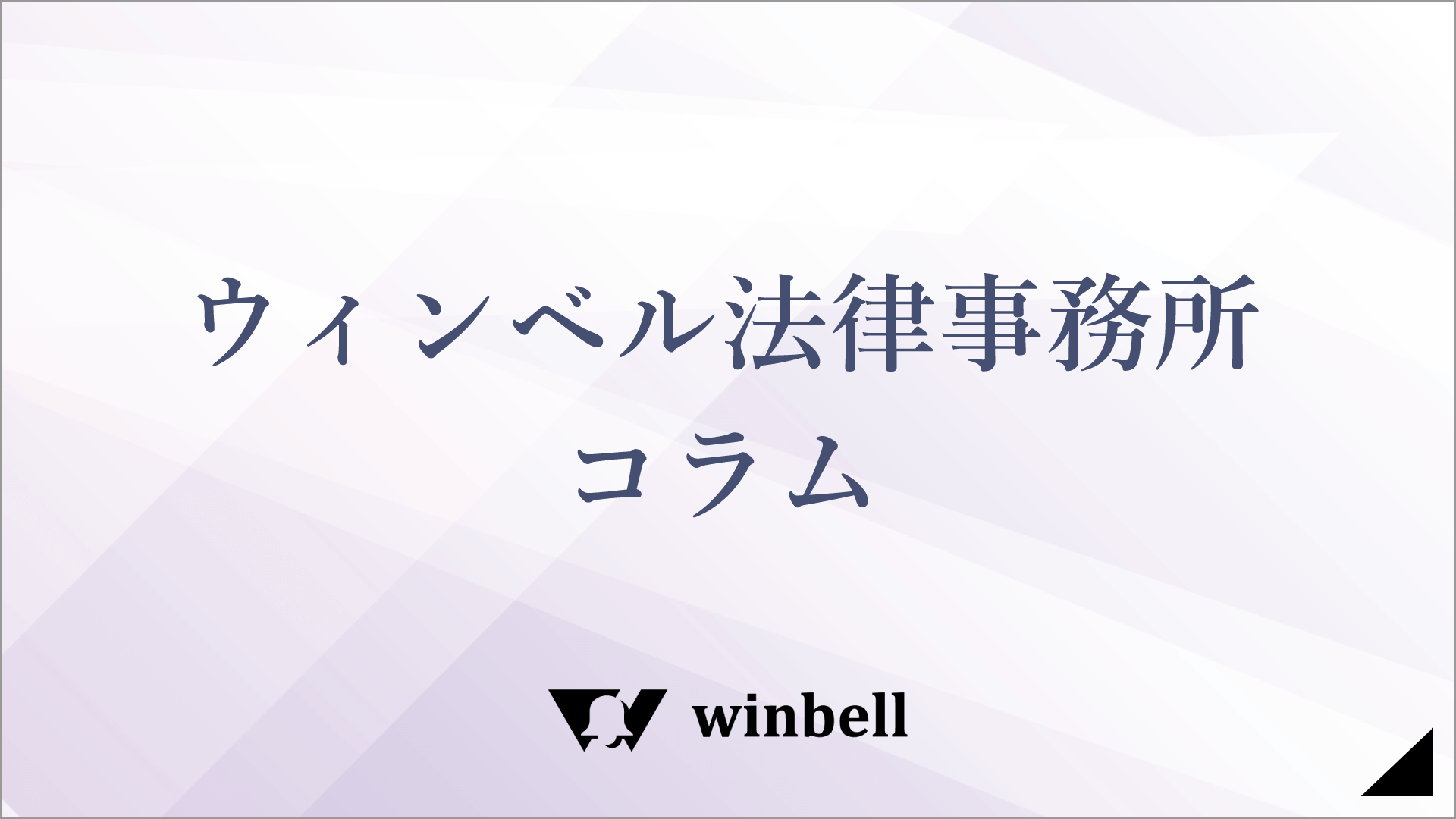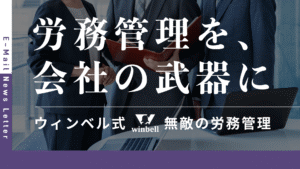従業員の過半数代表者の選出(その②)|ウィンベル式無敵の労務管理Vol.37

従業員の過半数代表者の選出
-その②-

ウィンベルの山口です。
このメルマガでは、「クライアントの勝利の鐘(ウィンベル)を鳴らす」というビジョンの実現を目指す中で、
- 私が目指す弁護士像
- 私をどのように活用してほしいか
- 皆さんにとって有益だと思う情報の共有
などを週3回、午前8時30分ころに配信します。
是非お知り合いにも紹介してください。
[登録用URL]https://39auto.biz/winbell/registp/entryform2.htm
金曜日の今日は、「ウィンベル式無敵の労務管理」を配信します。
さて、本題です。
今回も従業員の過半数代表者の選出方法についてお話したいと思います。
前回は行政の考えについて確認しました。
今回は、司法(裁判所)の考えを見ていきましょう。
- ①東京地裁令和2年2月27日判決
-
過半数代表者の候補を信任しない場合、締切までにその旨を記載した書面の提出を求めた事案
選任方法に不適切な点があったということはできないと判断
- ②松山地裁令和5年12月20日判決
-
過半数代表者の選出手続規程に信任投票において選挙権者が投票しなかった場合は有効投票による決定に委ねたものとみなすと定めてあった事案
有効投票による決定内容を事前に把握することはできず、また信任の意思表示に代替するものとして投票をしないという行動をあえて採ったとも認められないとして、選任された者が過半数代表者としては認められないと判断
さて、このような行政と司法の考えを踏まえて、実際の現場ではどうすればいいのかを考えてみましょう。
まず、行政の考えを前提とすれば、従業員の意見が明確になるような手段を講じることが適切であるとしています。
しかし、意見表明を行わない従業員に対してまで、逐一その意見を確認するのは煩雑です(従業員が多ければ余計に)。
そこで、そのような実態も考慮して、司法は、事前に締切を定めて「それまでに意見を表明しない場合は信任したものとみなす」という手続きを定めていれば、その選任方法は問題ないとしたと考えられます。
ただ、上記②の裁判例のように意見表明をしない場合に、その意思を不確定な内容としてみなすことはできません。
つまり、意見表明をしない場合に「信任」もしくは「不信任」とみなすという規定であれば問題ないことになります。
そして、手続きを簡便にするために、「信任」とみなすという形にするのがよいでしょう。
具体的には、メールや書面等で従業員に対して、従業員の代表者として●●氏が立候補していることを伝え、「●●氏が代表者として信任しない者は●月●日までに不信任である旨のメールまたは書面の提示をしなければ、候補者を信任したものとみなす」ことを伝えることになります。
もしくは、同内容の代表者選出手続きを定めておくことになります。
ただし、このような選出方法はある程度従業員が多く、全員が集まることが困難な場合には有効と判断されると思いますが、従業員が少ない場合はこの方法は認められないと裁判所が判断する可能性があります。
そこで、従業員が少なくミーティングや朝礼等従業員が一同に集まる機会が定期的にある場合は、その場で選出するのがオススメです。
立候補を募り、その場で立候補者を代表者として不信任の者について挙手を求める方法です。
この方法がもっとも簡単だと思います。
なお、その際は、必ず議事録を作成し、記録しておいてください。
以上のように従業員代表者の選出は意外と経営者にとっては不安になることも多いと思いますが、紹介した方法で選出していただければと思います。
本日は以上です。
それでは、よい一日を。
バックナンバーはこちら 弁護士山口への質問箱